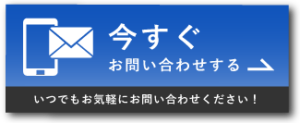少子化が進む日本社会においても、児童発達支援の需要は年々拡大を続けています。発達に特性のある子どもたちに合わせた「個別療育」への関心が高まり、家庭・行政・地域が一体となって早期支援を求める流れが加速しています。
それに伴い、安定した社会貢献型の福祉ビジネス参入を検討する法人や個人事業主も急増中です。
このページでは、最新の市場データと制度背景をわかりやすく整理しながら、なぜ今フランチャイズとして「ゆめラボ」が全国で選ばれているのかを詳しく解説します。
市場の現在地:数字で見る「児童発達支援 市場」
まずは児童発達支援市場の現状を数字で見てみましょう。国による制度整備と、保護者の理解の広がりによって、児童発達支援事業は急速に広がりを見せています。これまで専門性の高い一部の施設に限られていた支援が、今や地域単位で必要とされる社会インフラになりつつあります。
10年で費用額は約4.3倍、利用者数・事業所数も右肩上がり
児童発達支援にかかる総費用額は2012年の約415億円から2021年には約1,803億円に達し、わずか10年で4倍以上の市場規模に拡大しました。
同期間に利用者数は月平均4.7万人から13.6万人へ、事業所数も約2,000か所から約9,000か所へ増加。
まさに右肩上がりの成長を続けており、需要が高まり続ける業界の勢いを数字が物語っています。
未就学児が最も伸びるセグメント
中でも成長が著しいのが、0〜6歳の入学前の幼児層です。幼児期は発達支援の効果が最も出やすい時期であり、早期介入によって「できた!」という成功体験を積み重ねやすいのが特徴です。
保育園や幼稚園に加えて、児童発達支援事業所を利用する家庭も年々増加し、この層が市場成長をけん引しています。
潜在ニーズは65万人超、利用はまだ約3割
全国の0~5歳児のうち、発達に何らかの特性を持つ乳幼児は約65.6万人と推定されています。しかしそのうち実際に児童発達支援を利用しているのはわずか約3割。
残りの7割近い子どもたちは、支援が必要であっても十分に療育の機会を得られていません。
これは今後の拡大余地を示す大きな社会的課題であり、同時に成長余力のある市場であることを意味します。
制度背景:参入メリットを支える仕組み
児童発達支援は単なる民間ビジネスではなく、国が法制度として整備し、運営基準や報酬制度が明確に定められた認可福祉事業です。
行政による指定を受けることで社会的信用を確立し、安定した運営を行える点が最大の特徴です。
認可制(児童福祉法)による社会的信頼
児童発達支援は児童福祉法に基づく認可制であり、都道府県の指定を受けて開設・運営します。
行政・医療・教育機関との連携が求められる分野であり、地域との信頼構築を通じて安定的に運営できることが大きな強みです。
こうした制度基盤が、長期的な経営の安心感と福祉事業としての社会的価値を両立させています。
3~5歳は実質無償化:継続利用を後押し
近年の幼児教育・保育の無償化政策により、3~5歳児は実質的に自己負担なしで児童発達支援を利用可能になりました。
利用者は安心して通い続けることができ、事業者にとっても安定的な収益構造を築く要素となっています。
0~3歳児についても所得に応じた上限が設けられており、国全体として「早期支援を当たり前にする」流れが進んでいます。
福祉ビジネスとしての魅力:社会貢献×再現性
児童発達支援事業は、社会的使命と経営安定性を兼ね備えた新しい形の福祉ビジネスとして注目されています。
ゆめラボでは、この分野において再現性の高いモデルを構築し、未経験からでも参入しやすい体制を整えています。
社会課題の解決に直結する事業領域
既存の保育園やデイサービスでは十分に対応できなかった発達支援ニーズに応える形で、ゆめラボは個別療育中心の教室を展開。
多機能型にありがちな業務非効率を避け、1教室あたりの運営を最適化。採用・教育・集客を仕組み化することで、誰でも継続的に成果を出せるモデルを実現しています。
データで裏づけられた「通所頻度」と効果
児童発達支援における成果は、通所頻度に大きく影響します。
月1〜3回の利用では十分な変化が得られにくいのに対し、週2〜3回の通所を継続した場合、明確な成長変化が確認されることが多いとされています。
ゆめラボではこの「成果の見える通所モデル」を標準化し、効率的な運営と高い満足度を両立しています。
児童発達支援フランチャイズでゆめラボが選ばれる3つの理由
数ある児童発達支援フランチャイズの中で、ゆめラボが多くのオーナーや保護者から選ばれている理由は、「成果」「支援体制」「集客力」の3つに集約されます。
教育×福祉の専門性を活かした事業運営で、未経験者でも再現性の高い成功モデルを実現しています。
① 成果の出る個別療育モデル
TEACCHプログラムを基盤に、視覚支援・ほめる支援・体幹トレーニング・入学準備などをバランス良く組み合わせた独自の療育カリキュラムを導入。
一人ひとりの特性に合わせた支援で、「できた!」という成功体験を重ねることを大切にしています。
週2~3回の通所モデルを標準化することで、短期間でも成果が実感できる支援を可能にしています。
② 保護者支援を軸にした二重のサポート
「お母さんの笑顔が子どもの笑顔をつくる」という理念のもと、ゆめラボでは家庭との連携を何よりも重視しています。
保護者面談・家庭支援ツール・日々の記録共有を通じて、保護者が安心して子どもの成長を見守れる仕組みを構築。
保護者支援50%・子ども支援50%という考え方が、長期的な信頼と満足度を支えています。
③ 集客・求人の再現性:SEO×SNS×紙媒体のフルスタック
福祉分野では珍しく、ゆめラボは開業時からSEO・SNS・地域密着の広報戦略を融合。
自社HPのSEO対策に加え、Instagram・TikTokなどSNS投稿のテンプレート化、地域紙やポスティングを組み合わせ、オーナーが無理なく継続発信できる仕組みを整備しています。
開所初期から安定した認知・集客を実現するためのサポート体制も充実しています。
さらに、ゆめラボは自社公式サイトからの求人力が非常に高い点も特徴です。
Google検索で上位表示される構造をベースに、求人情報・インタビュー・働き方紹介などを体系的に発信することで、地域内での採用認知度を短期間で高める仕組みを確立しています。
結果として、求人媒体に依存せずに応募が集まりやすく、採用コストを抑えながら安定した人材確保が可能です。
本部のサポートを受けながら、開所初期から認知・集客・求人の3本柱を同時に成長させられること、それがゆめラボフランチャイズの強みです。
まとめ|まずは資料請求・ご相談から
児童発達支援市場は、「潜在ニーズが大きい」「制度に裏づけがある」「成果モデルが再現できる」という3点で、今後も成長を続けることが確実視されています。
ゆめラボは全国で同一クオリティの療育を提供することを目指し、理念に共感する仲間と共に拡大中です。
社会貢献と安定経営を両立できる福祉フランチャイズとして、ぜひこの機会にゆめラボの可能性を感じてください。
資料請求・ご相談は以下よりお気軽にどうぞ。